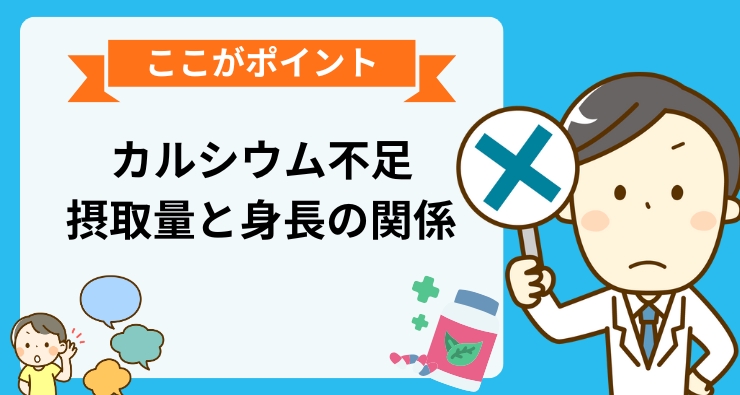「子供に積極的に摂らせたい栄養素は?」
このように質問すると「カルシウム」とお答えになる方が多いのではないでしょうか。
しかし、カルシウムは一体なんのために必要なのか、どうして子供に摂取すべきかを明確に答えるのは難しいでしょう。
一方で、カルシウムに関しては都市伝説のような不確かな知識も世の中にあふれています。
確かにカルシウムは子供をサポートする栄養素の一つで、成長期には不足しがちです。ですが、知識を知らなければ正しい摂取方法はわかりません。今回はカルシウムの正しい知識を身につけて、子供の成長に役立ててあげましょう。
成長途中の”小学生”
おすすめ身長サプリ
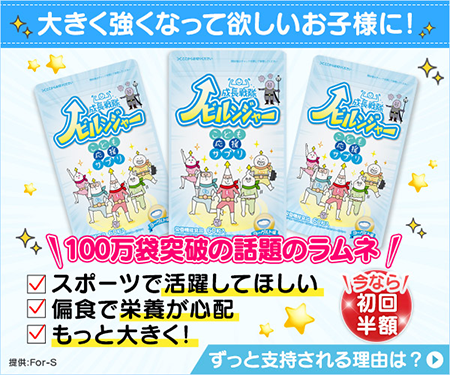
小学生は急激な成長にともない多くの栄養素が必要になります。この時期は身長が伸びる見逃せない大切な時期。
そんな時期におすすめしたいのが「成長戦隊ノビルンジャー」。
不足栄養素を配合して伸びやすい体作りをサポート。サプリ専門家が評価する”小学生に飲んでほしい身長サプリ(初回50%OFFも魅力的♪)。
▼公式サイトならではのお得な条件▼
成長途中の”中学生”
おすすめ身長サプリ
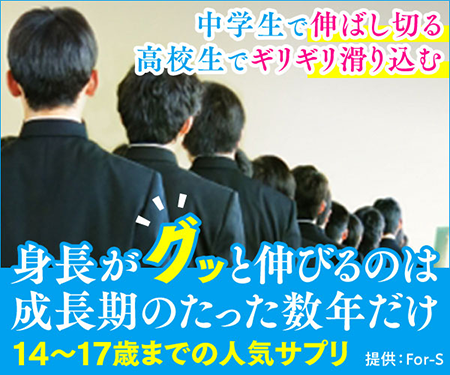
中学生、高校生は成長スパート期を迎え、人生の中で最も身長が伸びる時期です。そんな時期に必要となる栄養素は大人を超える量になります。
そんな栄養素をバランスよく配合したのが「ノビエース」。
ココア味なので好き嫌いなく飲めます。中・高校生は身長が伸びる最後の時期。しっかり栄養をサポートしてあげましょう!
▼公式サイトならではのお得な条件▼
カルシウムはどんな栄養素?
人間に必要な五大栄養成分は炭水化物、脂質、タンパク質、ビタミン、ミネラルのうち、カルシウムはミネラルに分類されます。ミネラルとは、地球上に元から存在する金属元素のうち、人間の生命活動に必須のものを指した言葉です。
人間の体の一番硬い部分である骨も、カルシウムによってできています。
さらに、カルシウムには他に大きな役割があります。
カルシウムの役割
カルシウムは生命活動の重要な部分を担っているミネラルです。筋肉細胞が収縮して力を発揮するためには、カルシウムを取り込まなくてはなりません。逆に、弛緩して力を緩める際にはカルシウムを放出する仕組みになっています。
さらに、神経に伝わるシグナルもカルシウムによって正常を保たれていて、怪我をして出血した際に血液が固まるのもカルシウムによるものです。
骨を強くするイメージが強いと思いますが、生命活動になくてはならないのがカルシウムという栄養素です。
血液やリンパ液など体液中のカルシウム濃度は常に一定に保つ必要があります。そのため、外から補給されないと貯蔵庫に貯めていたカルシウムを出庫して使うことになります。その貯蔵庫とは「骨」のことです。
体内のカルシウムの99%は骨に貯め込まれていて、残り1%が血液やリンパ液など体液中にあります。この1%が生命活動に重要な役割を担っています。子供にとって身長をサポートするだけでなく、体全体の成長に重要な栄養素の一つです。
カルシウムは、体重の1~2%(体重50kgの成人で約1kg)含まれており、生体内に最も多く存在するミネラルです。その99%はリン酸と結合したリン酸カルシウム(ハイドロキシアパタイト)として骨や歯などの硬組織に存在し、残り1%は血液、筋肉、神経などの軟組織にイオンや種々の塩として存在しています。
子供のカルシウム不足は行政機関も問題視
日本人は地質学的見地から見ても、慢性的にカルシウム不足の民族だと言われています。日本列島が火山によって形成された島であるため、土壌に含まれるカルシウムが少なく、飲水や農作物からカルシウムが摂り難いからです。
フランスなどは国土の55%がカルシウムを多く含む石灰質土壌です。これは、太古の生物の死骸が堆積して作られた土地だからです。そのため、フランスの飲料水や作物にはカルシウムが多く含まれ、日常的にカルシウムを摂取しています。
しかし、日本人は小魚などを骨ごと食べたりして、海産物からカルシウムを補ってきました。近年に入ると、牛乳などの乳製品からも、カルシウムを摂取するようになりました。しかし現在、特に子供において魚や牛乳の消費量は減少を続けています。
魚嫌いや牛乳嫌い、さらにはアレルギーの子供が増えたために小魚や乳製品の消費が減り、そのために子供が摂取するカルシウムはどんどん減少しています。成長期にある子供にはカルシウムが必要になる栄養素の一つとなるため、この状況は問題です。
厚生労働省は子供のカルシウム不足を懸念していて、子供の健やかな成長を目的とした施策「健康日本21」においても、栄養・食生活の目標の中に、脂肪や食塩の摂取量の減少とともに、カルシウム摂取量の増加を取り挙げているほどです。
子どもの食生活の状況を、独立行政法人日本スポーツ振興センターが2007年に全国の小学5年生を対象に実施した「児童生徒の食事状況調査報告書」によると、図5に示すように、給食のある日は、ほぼ所要量を充足しているのに対し、給食のない日はカルシウム、鉄の不足がみられる。
引用元:文部科学省「食生活学習教材」
このように、子供の成長をサポートするために必要な栄養素でありながら、常に不足しがちになっているのがカルシウムです。正しい摂取方法を知って積極的に摂取できるように目指しましょう。
カルシウムは骨の成長に関わる栄養素
子どもの骨をレントゲンで見ると、関節と骨の間に黒い線のようなものが確認できます。これを、骨端線と呼びます。成長が止まった大人にはこの線は現れません。骨が成長している証拠がこの「骨端線」です。
まず骨の先端にコラーゲンによる軟骨が形成されます。コラーゲンとは、たんぱく質の一種で、格子状に配列することで骨に柔軟性をもたせる役割を持っています。コラーゲンはレントゲンに映らないので黒い線のように見えます。
もちろん、軟骨のままでは骨として未完成です。骨とは柔軟性と強靭さを併せ持つ必要があります。柔軟性を担っているのがコラーゲンならば、強靭さを担うのがカルシウムです。骨端線にカルシウムが定着することで骨が作られます。
子供の成長には骨端線が大切
軟骨にカルシウムが定着することによって硬い骨となると、レントゲンに白い骨の形になって写るようになり、その部分の骨端線が消え新たに骨端線が現れます。このプロセスを繰り返して、少しずつ骨が成長していきます。
骨が成長する際には、骨全体が伸びていくようなイメージがありますがそうではありません。骨端線の部分にカルシウムが定着して骨が作られていきます。その結果、身長が伸びていくということに繋がります。
子供の身長が伸びるには骨端線が成長して骨が長くなることが必要です。そのために必要な栄養素の一つにカルシウムがあります。骨以外でも重要なカルシウムですから、成長期こそカルシウムを毎日摂取するのが理想です。
カルシウム・マグネシウム・ビタミンDの関係性
子供の身長を伸ばすならば「骨の成長」をサポートすることが大切です。そのために必要なミネラルはカルシウムだけではありません。
マグネシウムも骨や体の成長にとってなくてはならないミネラルです。
マグネシウムの関係性
マグネシウムは、エネルギー代謝などのために必要な酵素の原料となります。したがってマグネシウムも体内での濃度は一定に保たれる必要があり、一定量が骨に保管されています。つまり、マグネシウムも骨を構成する栄養素です。
ところが、カルシウムとマグネシウムには困った一面があります。食事で摂取されたこれらのミネラルは腸から吸収されるのですが、吸収率が非常に悪いです。それを補ってくれるのがビタミンDです。
ビタミンDの関係性
ビタミンDは、カルシウムやマグネシウムなどの腸管からの吸収を促進し、さらに腎臓からの排泄を抑制するためにカルシウムやマグネシウムの体内での濃度を一定に保ちます。したがって骨の形成にも関わるビタミンの一つです。
カルシウムを積極的に摂るとともに、マグネシウムやビタミンDなどの栄養成分も一緒に摂るように心がければ、子供の成長をサポートできます。食事からバランスよく栄養素を摂取することを心がけましょう。
骨の成長にはカルシウムだけじゃ足りない?
骨はカルシウムだけでできているわけではありません。カルシウムは硬い金属ですが、それだけでは脆く折れやすくなってしまいます。骨にはある程度のしなやかさと柔軟性が必要です。そのために必要なのがコラーゲンです。
骨はコラーゲンが格子のように張り巡らされ、その中にカルシウムなどの金属が収められています。こうして柔軟さと強靭さを兼ね備えています。さらに、骨が成長するときも最初にコラーゲンの軟骨(骨端線)が作られます。
このように骨の成長にはコラーゲンが必須ですが、実はコラーゲンはタンパク質の一種です。皮膚の土台や腱の材料となります。体内のタンパク質のうち30%を占めているのがコラーゲンです。
子供の身長をサポートするためにはコラーゲンも必要です。コラーゲンは体内で合成されるため、その材料となる栄養成分であるタンパク質(アミノ酸)もしっかり摂取することが理想です。
カルシウムは成長や身長サポートに欠かせない栄養素の一つ
カルシウムは、私達の日々の生命活動になくてはならない栄養成分だということが分かってきました。神経の伝達に重要なシグナル因子として働き、筋肉を収縮させて力を発揮するスイッチとなる物質であるからです。
そのため、体内には一定濃度のカルシウムが常に存在しなければなりません。カルシウムの濃度が低下すると、骨からカルシウムが持ち出され骨が脆くなってしまいます。したがって、毎日の食事でカルシウムを摂取するのが望ましいとされています。
そんなカルシウムは、成長期の子供にとってはさらに重要な栄養素の一つとなり、大人以上に必要となります。
では我々日本人にとって不足しがちな栄養素の一つであるカルシウムを、効率よく摂取するためにはどうしたら良いのでしょうか。
そして、子供の身長をサポートするためにはどのように摂るべきなのでしょうか。次項から考えていきます。
子供はカルシウムがどれくらい必要なの?
子供はカルシウムがどれくらい摂れているのか気になる方もいるでしょう。そこで厚生労働省の情報をもとに「推奨量」と「平均摂取量」を解説していきます。
情報は「日本人の食事摂取基準(2015年版)の概要」と「平成28年国民健康・栄養調査の結果」を参考にしています。
6歳~17歳までの推奨摂取量を男女別で紹介
| 男の子 | 女の子 | |
|---|---|---|
| 3歳~7歳 | 600mg | 550mg |
| 8歳~9歳 | 650mg | 750mg |
| 10歳~11歳 | 700mg | 750mg |
| 12歳~14歳 | 1000mg | 800mg |
| 15歳~17歳 | 800mg | 650mg |
参照:平成28年国民健康・栄養調査の結果
毎日の食事で摂取する平均摂取量
| 男の子 | 女の子 | |
|---|---|---|
| 1歳~6歳 | 421mg | 398mg |
| 7歳~14歳 | 678mg | 610mg |
| 15歳~19歳 | 508mg | 426mg |
参照:平成28年国民健康・栄養調査の結果
カルシウムが不足すると子供の成長にどう影響するのか
子供の身長をサポートするための栄養素の一つとしてカルシウムがあり、相当量必要であるということが分かって頂けたはずです。
では逆にカルシウムが不足した状態が続くと、子供の体にはどのような影響が出てくるのでしょうか。
目に見える影響だけでなく、そこには様々な可能性が待ち受けています。
骨粗しょう症の可能性
成長期の子どもは成人に比べて骨の成長が活発です。骨量が増加するこの時期に骨を丈夫にしておくことが、将来に向けて骨粗しょう症を防ぐことにつながります。丈夫な骨や歯をつくるためには、バランスのよい食事と運動が大切ですが、特にカルシウムはしっかりとりたい栄養素です。
カルシウムは骨の材料になるだけではなく、筋肉を動かしたりといった生命活動に重要な役割を担っています。したがって、体内に一定濃度のカルシウムが必須であり、足りなくなると骨からカルシウムを取り出す必要があります。
そのため長い間カルシウム不足の状態が続くと、骨からカルシウムが過剰に取り出されてしまい、骨がスカスカになってしまう可能性があります。
情緒が不安定になる可能性
かつて、校内暴力や若年層の犯罪が増えた頃に盛んに言われていたのが「若者のカルシウムが足りていないからだ」という主張です。
今どきこのような主張を掲げる方はいませんが、実はこの説にはしっかりとした論拠があります。
実は神経伝達においてカルシウムには非常に重要な役割があります。神経の間のシグナルを運ぶ役目を担っているのがカルシウムであるのと同時に、神経の興奮を鎮める働きを持っているのもカルシウムです。
カルシウムが少なくなると、運動神経や骨格筋の興奮が収まらなくなり、筋肉が痙攣しやすくなることが分かっています。ですので、興奮しやすい人などに「カルシウムが足りないのでは」というジョークが生まれたわけです。
カルシウムが神経伝達に大きく関わっていることは事実です。不足すると、情緒不安定になるなど成長期の子供に影響がでる可能性も否定できません。成長だけでなく、心にも必要な栄養素がカルシウムだとわかります。
カルシウムの過剰摂取による副作用や危険性は?
カルシウムが子供の身長をサポートするために必要な栄養素の一つであることはすでにお分かりだと思います。
では逆にカルシウムを摂りすぎてしまった場合、副作用などはないのでしょうか。
例えばサプリメントだと、一度にたくさん摂取できてしまいます。では、カルシウムが体内に大量に流入してきた場合の可能性を見てみましょう。
通常の食事で過剰摂取になる可能性は低い
カルシウムの摂取上限は、男女ともに1日2500mgと定められています。
この2500mgという量は、牛乳ならば2リットル強、丸干しイワシならば23尾弱、ちりめんじゃこなら500g、小松菜ならば1.5kgの含有量に相当します。一日に食べる量としては多すぎます。
その上、カルシウムは腸での吸収率が非常によくありません。カルシウムの吸収率は食品によって違いますが、牛乳では約40%、小魚では約33%、野菜からは約19%しか吸収されないというデータもあります。
カルシウムの吸収率は牛乳は40%と高く、小魚は33%、野菜は19%と食品によって違います。
引用元:日本乳牛協会
普段の食事ではカルシウムの過剰摂取を心配するどころか、子供の成長をサポートするために必要な推奨量を摂取すること自体、なかなか難しいことがお分かりいただけると思います。
一度の摂取は500mg以下が吸収率◎
カルシウムは非常に吸収しづらい栄養素の一つです。その上、一度に大量に摂取すると人間の体は吸収しきれないカルシウムを便や尿の形で外に排出してしまいます。そのため、多く摂れば摂るほど吸収率は低下します。
研究によると、一度に摂るカルシウムの量が500mgを超えると、腸管からの吸収率がどんどん低下していくという結果が出ています。
カルシウム吸収率は1度に消費されたカルシウム元素の総量に依存する。総量が多いほど、吸収率は下がる。吸収率は500mg以下で最も高くなる[1]。例えば、カルシウム1,000mg/日をサプリメントから摂取している場合、投与回数を分割して、1日2回500mgずつ摂取しても構わない。
引用元:厚生労働省eJIM
つまり、一度に摂取するならば500mg以下が吸収率が高いということです。
子供の身長をサポートしようとして、サプリメントなどで一度に大量のカルシウムを摂取するのはやめましょう。後述するような影響が出る可能性もあります。
サプリメントによる過剰摂取に注意
吸収効率が悪い栄養成分であるカルシウムですが、サプリメントなどで過剰摂取すると吸収率も悪くなり本末転倒です。
子供の身長をサポートするならカルシウムの集中投下ではなく、日々の積み重ねで伸びていくものだと肝に銘じましょう。
カルシウムがたくさん摂れる食品一覧
栄養成分表などからカルシウムの含有量が多い食品を拾い上げると、干しえび、がん漬(カニの塩辛)、乾燥バジルなどが上位に来ます。しかし、これらは100gでの含有量なので、これらの食品を100gとることは現実的ではありません。
そこでまず摂取量で比較し、さらには子供の身長と骨の成長を考え、日々の食卓でお母さんたちが料理として出しやすい食品のなかから、カルシウムをたくさん摂れる順で表を作成してみました。
| 1 | 干しエビ10g(カルシウム量710mg) |
|---|---|
| 2 | 生揚げ1枚(288mg) |
| 3 | 牛乳一杯(220mg) |
| 4 | ししゃも3尾(198mg) |
| 5 | 小松菜1/4束(162mg) |
| 6 | イワシ丸干し1尾(132mg) |
| 7 | 木綿豆腐半丁(129mg) |
こうしてみると、魚介類、乳製品、大豆食品が子供にも与えやすく、カルシウム含有量が多い食品だと言えます。
これらの食品を上手に取り入れることが、子供のカルシウム不足を少しでも解消する手がかりとなるでしょう。
カルシウムのサポートを目的とした成長補助食品(身長サプリ)
成長期にある子供たちにとってカルシウムは大切な栄養素の一つであるにもかかわらず、不足しがちな栄養素の一つです。厚生労働省も注意喚起するほどの状況ですが、なかなか打開策がみつかりません。
| 推奨摂取量 | 平均摂取量 | 過不足 | |
|---|---|---|---|
| 0~5ヶ月 | 男:200mg | 男:データなし | 男:データなし |
| 女:200mg | 女:データなし | 女:データなし | |
| 6~11か月 | 男:250mg | 男:データなし | 男:データなし |
| 女:250mg | 女:データなし | 女:データなし | |
| 1~2歳 | 男:450mg | 男:421mg | なし |
| 女:400mg | 女:398mg | なし | |
| 3~5歳 | 男:600mg | 男:421mg | 男:179mg |
| 女:550mg | 女:398mg | 女:152mg | |
| 6~7歳 | 男:600mg | 男:678mg | なし |
| 女:550mg | 女:610mg | なし | |
| 8~9歳 | 男:650mg | 男:678mg | なし |
| 女:750mg | 女:610mg | 女:140mg | |
| 10~11歳 | 男:700mg | 男:678mg | 男:22mg |
| 女:750mg | 女:610mg | 女:140mg | |
| 12~14歳 | 男:1000mg | 男:678mg | 男:322mg |
| 女:800mg | 女:610mg | 女:190mg | |
| 15~17歳 | 男:800mg | 男:508mg | 男:292mg |
| 女:650mg | 女:610mg | 女:40mg | |
| ※上記データは厚生労働省の「国民健康・栄養調査」と「日本人の食事摂取基準2015年度版」から算出した数値を比較。 | |||
その理由は、カルシウム自体が摂取しづらい栄養素であるとともに、体にも吸収しづらい栄養素だからです。
そこで、選択肢の一つとして活用できるのが『子供用サプリメント』です。
あくまで食事がベースになりますが、子供の成長に合わせて栄養素が配合されたサプリメントならば、吸収率も考慮されマグネシウムやビタミンD、さらにはたんぱく質など身長をサポートするために必要な栄養素が数多く配合されています。
サプリメントの場合、カルシウム含有量が計算されていて一日の摂取量が記載されています。
成長期の子供たちになくてはならない「カルシウム」ですが、食事とあわせて子供用サプリメントを活用するのも一つの手段です。
成長途中の”小学生”
おすすめ身長サプリ
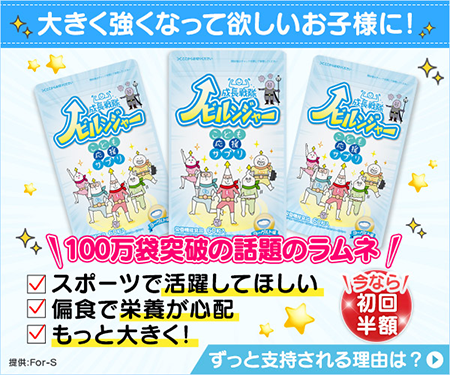
小学生は急激な成長にともない多くの栄養素が必要になります。この時期は身長が伸びる見逃せない大切な時期。
そんな時期におすすめしたいのが「成長戦隊ノビルンジャー」。
不足栄養素を配合して伸びやすい体作りをサポート。サプリ専門家が評価する”小学生に飲んでほしい身長サプリ(初回50%OFFも魅力的♪)。
▼公式サイトならではのお得な条件▼
成長途中の”中学生”
おすすめ身長サプリ
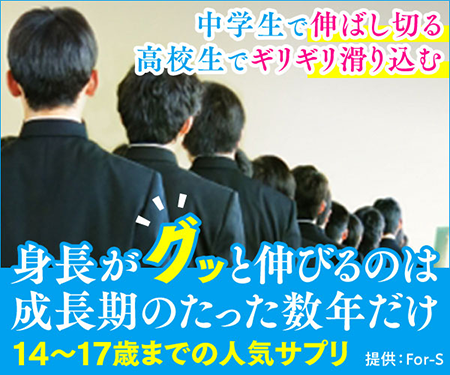
中学生、高校生は成長スパート期を迎え、人生の中で最も身長が伸びる時期です。そんな時期に必要となる栄養素は大人を超える量になります。
そんな栄養素をバランスよく配合したのが「ノビエース」。
ココア味なので好き嫌いなく飲めます。中・高校生は身長が伸びる最後の時期。しっかり栄養をサポートしてあげましょう!
▼公式サイトならではのお得な条件▼
まとめ
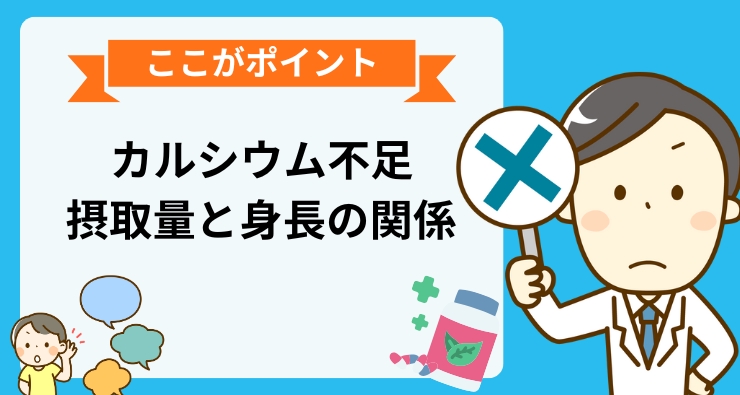
カルシウムは骨の材料となって身長をサポートするだけでなく、筋肉の収縮や神経の伝達などに必要であり、体の成長にはなくてはならない栄養素です。しかし、成長期の子どもはカルシウムが不足しがちになり問題視されています。
繰り返しになりますが、骨の成長にはコラーゲンによる軟骨(骨端線)が形成され、その部分にカルシウムが吸着することで少しずつ骨が伸びていき身長が伸びます。
カルシウムを過剰摂取すると弊害はありますが、小魚などの摂取量が減っている現代では食事でなかなか推奨量を満たていないのが現実です。
サプリメントも一つの選択肢として
サプリメントは摂取する量が厳密に計算されて配合されているので、効率よくカルシウムをサポートすることができます。
また、吸収を高めるビタミンDやマグネシウム、タンパク質などをバランスよく配合したものも販売されています。