どのような基準で子ども用のサプリメントを選んでいますか。
価格や口コミで選ぶ方法もありますが、欠かせない一つの指標に「製品の品質や安全性」があります。
当然ながら、子供が口にするものですから、その製品の安全性はとても重要な指標です。
では、どのようにしてサプリメントの安全性を確かめればいいのでしょうか。
その基準となるのが「GMP」です。
まずはGMPの基礎から安全性との関係性、どのような商品に認定されているのかを解説していきます。

厚生労働省も推奨するGMPとは

GMPは、その名の通りアメリカ発祥の概念です。「Good Manufacturing Practice」の略で日本語では「良い製造の規範」となります。
1938年にアメリカ食品医薬品局が定めた、食品や医薬品の製造品質管理基準です。
様々な国が同様の規範を設けており、日本においては昭和35年に定められた「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律」略称「医薬品医療機器法」に基づいて、厚生労働省が医薬品等の品質管理基準を設けました。
健康食品に GMP が必要な理由は?
健康食品(特に錠剤やカプセル状のもの)は、製造の過程で濃縮や混合などの作業が行われるため、製品中に含まれる成分量にバラつきがでたり、汚染などにより有害物質が混入したりする可能性があります。この問題を未然に防ぐためにGMPが導入されるようになりました。国際的にもGMPの義務化や自発的な取り組みが推進されています。
サプリメントの品質管理基準としては、厚生労働省が定めた「健康食品GMPガイドライン」というものがあります。
これに基づき、第三者機関が製造工場を審査して、合格したものにGMP認証が与えられGMP工場を名乗ることができます。
 日本ニュートリション協会公認のサプリメントアドバイザー
日本ニュートリション協会公認のサプリメントアドバイザーつまり、GMP認証された工場で作られた製品は一定の品質が保証されている訳です。
健康食品にGMPを推奨する理由とは
サプリメント製造において、その製造工程は我々消費者にはブラックボックスです。
- どのくらい衛生管理がなされているのか
- 原材料はどのように扱われているのか
- 表示された原料が、適切な量配合されているのか
これらを知る術はありません。
悪質な業者の場合、必要な栄養成分を十分配合していなかったり、成分を水増しする可能性も完全に否定できません。
そのような工場で製造されたサプリは到底安全とは言えず、子供に与えるわけにはいきません。
そんな製品を避けるための一つの品質管理基準として「GMP」が設けられています。特にサプリメントは健康のために口にするため、安全性や品質は重要な項目です。



品質の安全性が保証された商品を選ぶ基準として、GMP認証を確認することを忘れないでください。
GMPのガイドライン3原則
厚生労働省が定めた「健康食品GMPガイドライン」には、サプリメント製造において、その安全性を保つための目標を3つ掲げています。
それがGMPガイドライン3原則です。工場はその3原則を励行する義務があります。
| 原則 | 説明 |
|---|---|
| 原則 1 | 各製造工程における人為的な誤りの防止 |
| 原則 2 | 人為的な誤り以外の要因による製品そのものの汚染および品質低下の防止 |
| 原則 3 | 全製造工程を通じた一定の品質の確保 |
3原則の1つ目は「各製造工程における人為的な誤りの防止」です。製造工場は人間によって運営され、人為的なミスが発生する可能性があります。それをゼロに近づけるために、システムを構築しなくてはなりません。
2つ目は「人為的な誤り以外の要因による製品そのものの汚染および品質低下の防止」です。不衛生な環境による汚物や細菌の混入や、不適切な保管方法による原材料の品質劣化などを防ぐために、適正な製造環境を整えなければなりません。
そしてガイドラインの3つ目は「全製造工程を通じた一定の品質の確保」です。出来上がる商品によって品質が違ってしまっては、工場製品として不適切です。
GMP認定工場が行う品質管理の内容
GMP認定を受けただけでは、その工場の安全性が保証されたとは言い切れません。GMP認定を保持するために、日々の運行において厳密な品質管理を行う義務があります。
当然のことですが、常に製品には正しい原材料を適正な分量配合しなくてはなりませんし、異物の混入や他原料の混同が無いような配慮が必要です。
さらに、出来上がったサプリメントのチェック体制も重要です。原材料や賞味期限など、消費者に開示したスペックが満たされた品質が常に保たれているかを製造や出荷においてチェックするシステムを運用しなくてはなりません。
そして、万が一ミスが発生した場合に対する危機管理のシステムとして、製造や品質管理の記録が保管されている必要があります。製品のサンプルなどを残しておくことも重要です。GMP認定工場はこれらを励行しています。
GMPを認定する機関は2つある


サプリメント製造会社の工場がGMP認定を受けるには、第三者機関に申請を行いその機関から品質と安全性を保持しているかの審査を受けなければなりません。
この第三者機関は民間の団体であり、現在国内では2つの団体があります。それが「一般社団法人日本健康食品規格協会」と「公益財団法人日本健康・栄養食品協会」です。
日本におけるGMP認定工場およびその製品は、このどちらかの認定を受けることになります。
日本健康食品規格協会(JIHFS)
日本のサプリメントに対してGMP認証を行っている民間の第三者機関の一つが、日本健康食品規格協会です。
東京都の文京区本郷に本部がある一般社団法人です。
日本の健康食品の品質と安全性を高め、消費者の信頼性を得るために平成17年に設立された業界団体です。
厚生労働省のガイドラインに則ったGMPの普及・啓発を行うことを目的とし、そのための企業支援をおこなっています。
JIHFSは、既にスタートしている海外の健康食品GMPや医薬品GMPを参考にしながら、医療や様々な分野のエキスパートの助言をもとに「サプリメントのためのGMP」を作りました。おりしも厚生労働省は2005年2月1日付で、錠剤やカプセル状の形状をとる健康食品の品質と安全性の確保のための考え方として健康食品GMPガイドラインを発表し、業界が自らの努力でこの問題に取り組むように指導しています。
現在、52の企業が会員であり、およそ50の工場と370以上の製品にGMP認証されています。
業界団体であるのでその査察などは外部団体に委託しており、工場の監査などはNPO法人日本医薬品食品品質保証センターが行っています。
GMP認証だけでなく会員企業に対するサプリメントの安全性・品質確認試験を行ったり、GMPに関する社内研修を請け負ったり、サプリメント業界自身の発展を目標として様々な活動を行っているのがこの団体の特徴です。
公益財団法人日本健康・栄養食品協会
もう一つのGMP認証を行っている民間の第三者機関が、公益財団法人日本健康・栄養食品協会です。サプリメント製造などを含めた健康食品・栄養食品の適正な普及と業界の健全な発展を目的として設立された業界団体です。
昭和54年の発足以来、健康増進法の趣旨に則った食品の栄養表示の普及や、特定保健用食品(トクホ)認証の支援などの活動を行っています。
GMP認証を行う以前からJHFAマークでサプリの安全性・品質の保証を行っていました。
商品の中味である栄養成分や有用成分がきちんと表示通り含まれているのでしょうか。
そのような疑問や商品の安全性は誰が保証しているのでしょう。それらの疑問や不信を取り除くために、昭和60年に当時の厚生省が設置を認めた財団法人 日本健康・食品協会の事業として、健康食品の規格基準の設定とその基準に係わる認定制度を開始しました。
平成23年には厚生労働省から公共の利益に値することが認められ、公益財団法人となりました。
現在参加している団体は700社以上に上り、日本のサプリメント業界団体としては最大の財団法人として活動を続けています。
現在までに日本健康・栄養食品協会がGMP認定した工場は、海外も含めて140ヶ所以上、GMP認定した製品はおよそ150製品になります。
GMP認証事業はまだ日が浅いので、これからさらに増えていくことが見込まれます。
日本健康食品規格協会と日本健康・栄養食品協会の違い
日本健康食品規格協会(JIHFS)と、日本健康・栄養食品協会(日建栄協)はどちらもサプリメントや健康食品の製造企業を支援する業界団体です。
しかし、その両者の大きな違いは歴史と活動の目的にあると言えます。
JIHFSは、GMP認証のために設立された団体です。従って歴史も浅く会員企業も限られているのが特徴です。
一方で、日健栄協はGMPの概念が輸入される以前からJHFAマークなどを普及させ、健康食品の品質や安全性を高めてきました。
しかし、GMPに関してはどちらも厚労省のガイドラインに則った査察を行っており、1年ごとの監査や3年ごとの更新を行うなど大きな差はありません。どちらのGMPマークでも信用に値すると考えられます。
GMP以外にも企業によっては取得している認証がある
サプリメントや健康食品の品質や安全性に対する保証はGMPだけではありません。前述の日健栄協が認証するJHFAマークもその一つです。GMPの概念が導入される以前は、JHFAマークを取得した企業が多くありました。
さらに、同じく日健栄協では、健康食品の原材料などを含めた安全性の認証として「安全性自主点検認証」を行っています。
このように食品安全の認証には様々なものがあるため、企業によっては複数取得していることもあります。
日本健康・栄養食品協会のGMPマークは2つある
GMP認定工場(工場のみGMP認定)
日健栄協がGMP査察を行い、品質・安全性を保っていると認められた工場にはGMP認定が与えられます。これは、GMPに則った運営を過去3ヶ月間行ったという実績があれば申請でき、査察を経ると認定されることになります。
GMP認定を受けた工場では、会社案内のパンフレットやホームページに「GMP工場マーク」を使用することができます。さらに、工場やメーカーに勤める社員の名刺にも「GMP工場マーク」を印刷することが可能です。
ただし、GMP認証を受けた工場で作られたサプリメントだからと言って、そのパッケージにGMPマークを付けることはできません。製品にGMPマークを付けるためには製品ごとに審査を行い、認定を受ける必要があります。
GMP認定工場製品(工場だけでなく製品自体も審査をクリア)
日健栄協には、もうひとつ「GMP製品マーク」があります。これは、サプリメント自体がGMP認証を受け、品質や安全性が保たれていることが保証された商品であることを示し、パッケージなどに表示することが可能なものです。
「GMP製品マーク」を表示できる製品は、当然GMP認証された工場で作られていることが大前提となります。その上で、製品ごとに申請をし、日健栄協の「GMP製品表示審査会」において審査が行われ、交付されます。
その後は、10ヶ月ごとにGMP製品マークを表示するに値する品質を保っているか確認が行われ、3年後には再び審査が行われ継続可能か判断されることになります。
このようにGMPマークを掲示するには厳しい審査があります。
GMPよりも厳しい世界基準のNSF GMPがある


NSFは「National Sanitation Foundation(国民衛生財団)」の略で、NSF GMPとはNFSインターナショナルという機関が認証する、国際的な基準に則ったより厳しいGMP認証のことです。
NSFインターナショナルは1944年に設立された非営利の第三者認証機関で、ANSI(アメリカ規格協会)とSCC(カナダ規格評議会)から認定を受けています。また、WHO(世界保健機関)の協力センターに指定されています。
NSF GMP認定は国内のGMP認定よりも厳しく、品質や安全性に対しての基準を設けていると言われています。
国内のGMP認定を受けた工場で使われる材料でも、NSF GMP認定には通らないこともあります。
様々なメーカーがこのNSF GMPを取得することを目指していて、富士化学グループの米国のアスタキサンチン工場や、化粧品の東洋新薬、森下仁丹やサプリメントジャパンが認証されたとして大きなニュースになりました。
GMPについて注意すべきポイント
ここまで、GMPとはどういったものか、どのような製品にGMPが与えられるのか解説してきました。サプリメントの品質や安全性を判断するための目安として、GMPの認証の有り無しは一つの指針になると思われます。
しかし、GMPばかりが身長サプリを選ぶ基準ではありません。また、GMPとさえ記載されていれば全て安全であるという訳ではありません。ここでは、GMP表示をどのように受け止めたら良いのか、注意点を考えていきます。
GMP認定工場での製造、GMP認定工場製品でないと危険なの?
GMPの概念自体はアメリカで生まれたものです。そして、1969年にWHO(世界保健機関)が加盟各国に適用を勧告しました。しかし、GMPのガイドラインそのものは、製造業においては遵守することが当たり前のことです。
製造業においては、品質を一定に保ち、かつ製品の安全性を保証することは当然のことです。それがないと、消費者の信頼を得られず製品が売れなくなります。GMP認証がなくとも、それを守っているところもあります。
これは、サプリメントの製造業でも同じことです。



我が国には薬事法や製造者責任法など、品質や安全性を守るための法律が幾つも有り準拠しなくてはなりません。
GMP認証は、第三者機関が品質と安全性を保証したとして、より消費者に安心感を与えるためのものです。
しかしながら、あくまで基準の一つです。
前述のように、認証がなくても安心できるメーカーは幾つもあることを知っておいてください。
GMPの「準拠」と「認定」の違い
多くのメーカーが安心安全なサプリメント製造を目指していると言いましたが、一方でGMPという文字を都合よく使っているメーカーもあるので注意が必要です。闇雲に、「GMP」という文字だけを信頼してはいけません。
GMPに準拠した工場で、品質と安全性が第三者機関から保証された場合はGMP「認証」を受けた、ということができます。この場合、会社のパンフレットや製品に各団体から許可されたGMPマークを表示してあるはずです。
注意が必要なのがGMP「準拠」という書き方です。「準拠」とは、「それを標準として従うこと」という意味です。つまり、GMPのガイドラインに則った製造をしているという意味に過ぎず、GMPとは関係がありません。
GMP「準拠」という場合は第三者機関の審査等を経ておらず、「GMPに則ってますよ」と記載しているだけです。
サプリメントのGMP取得における日米間の違い
率直に言うと、日本はサプリメント後進国です。サプリメントや健康補助食品の文化自体が割と最近普及したもので、法整備も含めて欧米からは遅れています。
アメリカではFDA(アメリカ食品医薬品局)が先導して、国民が口にする食品や医薬品を厳しく管理しています。その考え方はGMPにも当然表れていて、そもそもGMPの基準をクリアしないと販売許可が下りないようになっています。
一方で、日本のGMPは基準であり、任意に守るべきとされるガイドラインに過ぎません。ですから、GMP認証が無くても製造販売に支障はありませんし、品質や安全性の保証はそれぞれのメーカーに委ねられていると言えます。



日本は性善説に則り、アメリカは性悪説に則っているといえるかもしれません。
GMP基準認定工場で製造の成長応援サプリ2選
成長途中の”小学生”
おすすめ身長サプリ
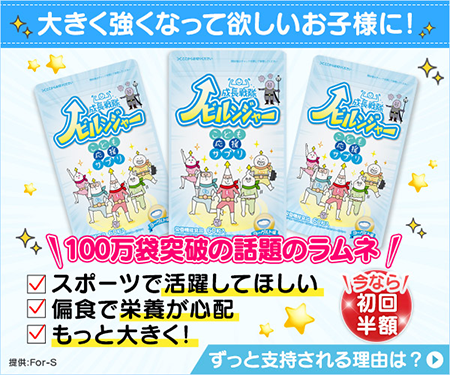
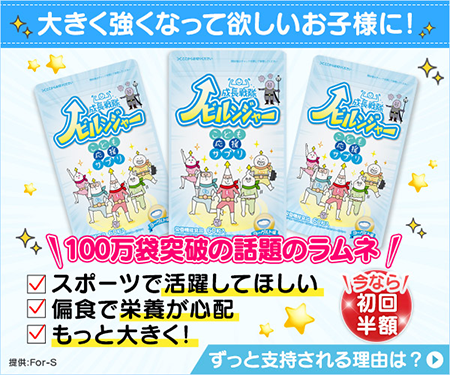
小学生は急激な成長にともない多くの栄養素が必要になります。この時期は身長が伸びる見逃せない大切な時期。
そんな時期におすすめしたいのが「成長戦隊ノビルンジャー」。
不足栄養素を配合して伸びやすい体作りをサポート。サプリ専門家が評価する”小学生に飲んでほしい身長サプリ(初回50%OFFも魅力的♪)。
▼公式サイトならではのお得な条件▼
成長途中の”中学生”
おすすめ身長サプリ
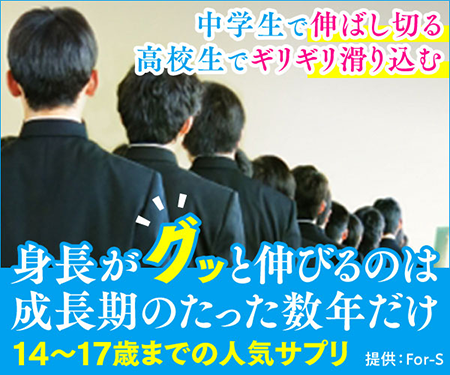
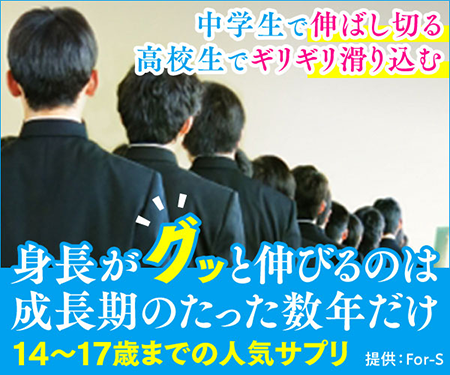
中学生、高校生は成長スパート期を迎え、人生の中で最も身長が伸びる時期です。そんな時期に必要となる栄養素は大人を超える量になります。
そんな栄養素をバランスよく配合したのが「ノビエース」。
ココア味なので好き嫌いなく飲めます。中・高校生は身長が伸びる最後の時期。しっかり栄養をサポートしてあげましょう!
▼公式サイトならではのお得な条件▼
まとめ
GMPとは、サプリメントの製造において品質を管理するための規範のことです。日本では、厚生労働省が製品製造におけるガイドラインを作り、それに則って第三者機関が安全性などを保証するためのGMP認証を行っています。
GMPのガイドラインとは、「工程における人為的な誤りの防止」「製品そのものの汚染および品質低下の防止」「一定の品質の確保」の三原則であり、各企業はそれを守るために様々な努力を怠らないようにしなければいけません。
GMP認証を行っている機関は日本では2つあります。日本健康食品規格協会と、日本健康・栄養食品協会です。



2つの機関のどちらも、1年毎の査察や3年毎の更新を行っています。健康・栄養食品協会の方が設立が古く、多くの企業が加盟しています。
工場を認定するGMPだけでなく、製品そのものが認定されるとパッケージ等にGMPマークが表示されます。
他にもJHFAマークや安全性自主点検認証など、品質保証のマークは様々で、国際的なNSF GMP認証というものもあります。
中にはGMP準拠などといって認証されていないのに表示をするメーカーもありますので注意が必要ですが、上記のようなマークや認証は、身長サプリを品質や安全性から選ぶ上での基準になります。


